受験生の子どもを持つ親として、「そろそろ志望校を決めなきゃ…」という時期がやってくると、なんとなく落ち着かない日々が始まりますよね。
子どもがどんな将来を思い描いているのか、どんな大学に行きたいと思っているのか、聞いても「まだ決めてない」「よくわからない」と言われてしまうこともあるかもしれません。
そんなとき、保護者としては不安や焦りが出てきます。
「大丈夫なのかな?」「こんな調子で間に合うの?」と、つい口出ししたくなったり、他のご家庭と比べて焦ってしまったり。
でも、私はこう思うのです。
志望校選びは、思いきり悩んでいい。
むしろ、たくさん悩んでこそ、本当に意味のある受験になると思います。
「大学に行く目的」は一つはない
「大学って、行くのが当たり前」
そんな空気の中で、子どもたちは漠然と進学を目指しています。
でも、じゃあ「なぜ大学に行きたいのか?」と聞かれると、はっきり答えられる高校生は、実は多くないと思います。
キャンパスがきれいだから。
サークル活動が楽しそうだから。
有名な大学だから。
友達が目指しているから。
そういう気持ち、私はとてもわかります。だって太郎も次郎もそうだったから。
目に見えるイメージから憧れを抱くことは、ごく自然なこと。
大学生活の中には、高校生の今からは想像もつかないような楽しいこと、充実した経験が本当にたくさん待っています。
だから「楽しそう」で選ぶのも、最初はアリなんです。
でも、そこから一歩踏み込んで「目的」を真剣に考えてほしいです。
学びたいこと、なりたい姿を少しずつ見つけていく
「将来どんな仕事をしたいのか」
「どんなことを深く学びたいのか」
「どんな自分でありたいのか」
今すぐ答えを出せなくてもいいんです。
でも、考えてみること、調べてみること、迷ってみること自体がとても大切なことだと思うのです。
大学は、「行くこと」自体がゴールではなくて、**その先を見据えるための“入り口”**です。
もし大学選びの基準が「周りに合わせたから」「親に勧められたから」だけだった場合、
入学してから「思っていたのと違った」「勉強が興味持てない」と感じてしまうことも少なくありません。
最悪の場合、大学に通う意味を見失い、途中でやめてしまうようなケースもあるのです。
保護者にできるのは、「急がせない」ことと「見守る」こと
私自身、双子の子どもをそれぞれ違う進路で見送りました。
理系大学を選んだ子、文系大学を選んだ子。
実際に太郎と次郎は志望校には届きませんでしたが、学ぶ内容。学部は真剣に悩んだ結果本人たちも納得して学ぶことができたようです。
受験生それぞれに、性格や興味、価値観を尊重して、親としてできることは「話を聞くこと」「調べる手助けをすること」くらいでした。
正直なところ、私もたくさん悩みました。頭がおかしくなるくらいに💦
「この選択で本当にいいのかな?」と不安になる場面も多々ありました。
でも、子どもが自分で選んだ道なら、たとえ大変なことがあってもきっと乗り越えられる。
そう信じて見守る覚悟を持ったとき、子ども自身も、自分の選択に納得して受験に臨んでいたと思います。
最後に──
志望校選びに悩むのは、子どもだけじゃありません。
親もまた、不安や迷いの中で、支え方を手探りしているのだと思います。
だからこそ、志望校選びは、親子で一緒に悩んでいい。
そして、焦らず、比べず、その子だけの「納得できる選択」を見つけていけたら、それが一番の進路につながると思うのです。
このブログでは、双子の受験を見守った保護者として、経験から学んだこと、感じたことを綴っています。
同じように迷いながら進んでいる方の、少しでも心の助けになればうれしいです。
にほんブログ村
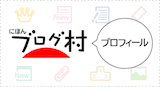

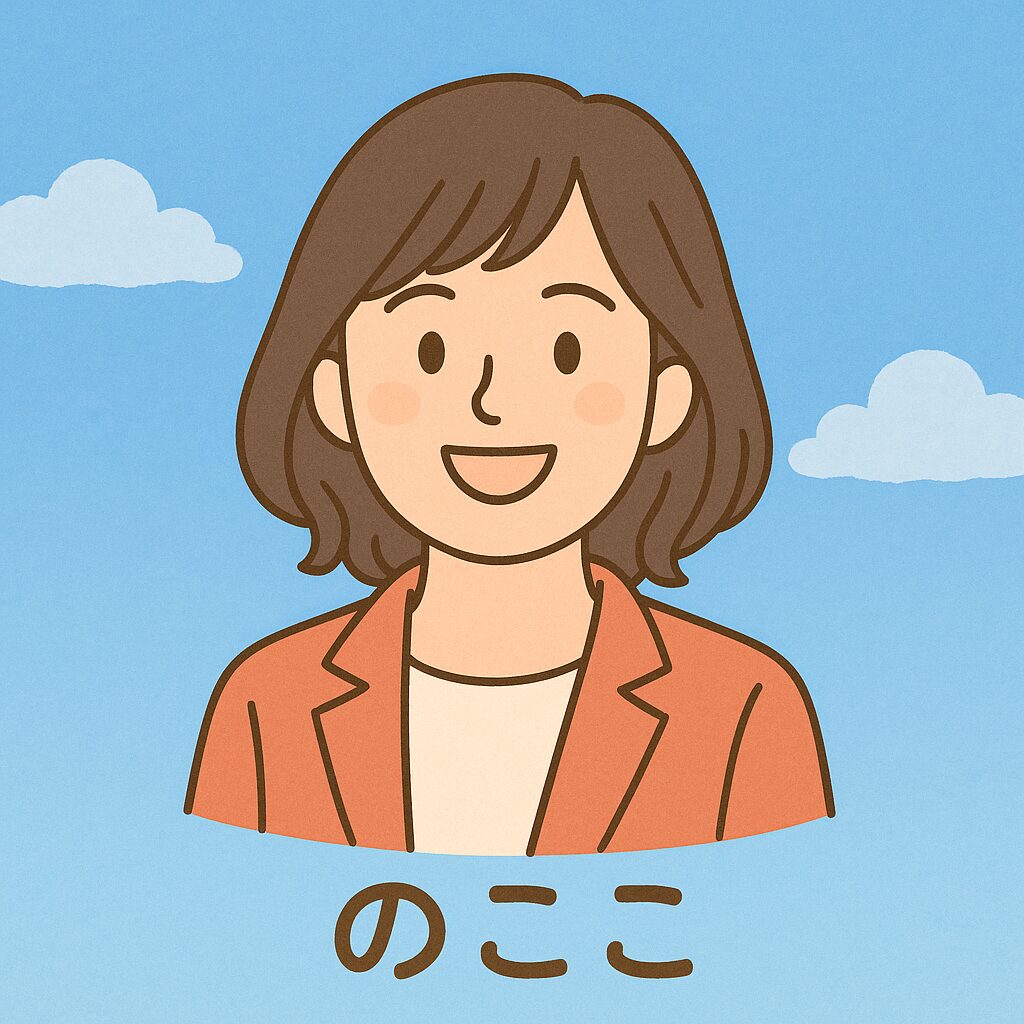

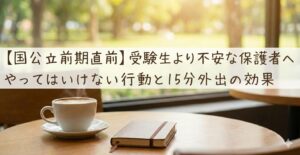


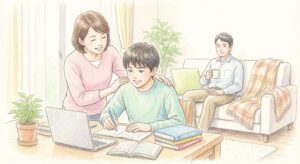
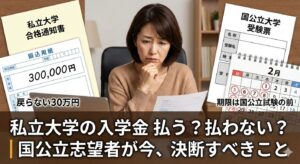


コメント