こんにちは。
今日は「模試を受ける意味ってあるの?」というテーマでお話しします。
双子の息子たちの大学受験を見守る中で、模試を何度も受けさせてきましたが、正直最初は「こんなに模試って必要?」と思っていました。料金もバカにならない😭
でも、実際に受験を経験してみると、模試には受けるだけの大きな意味があったと感じました。
1. 自分の“今の実力”を知るため
学校のテストはあくまで「その学校の中での順位」しかわからない。
でも模試は全国規模。
つまり、自分が今、
- 全国の中でどの位置にいるのか?
- 志望校との差はどれくらいあるのか?
を知ることができます。
息子たちも最初は偏差値を見てショックを受けていましたが、「あと何点でこの大学が狙える」とわかったことで、やる気につながっていたように思います。
2. 志望校選び・併願校のヒントになる
模試の判定(A〜E)や志望校一覧は、ただの評価ではありません。
「今のままだと厳しいけど、あと半年でこの大学を目指せる」
「安全校をここに変えておこう」など、
現実的な志望校選びにとても役立ちました。
特に、息子たちは一般入試だったので、出願戦略は親としても一緒に考えながら進めました。
3. 試験本番の“予行練習”になる
模試は本番さながらに行われるため、
- 時間配分
- 集中力の持続
- マークミスのチェック
など、受験の“場慣れ”としてすごく大事です。
共通テスト形式の模試は特に、午前から午後までの長丁場。
体力や集中力を保つコツを身につけるには、実戦形式の模試が一番効果的だと感じました。
4. 弱点発見と“今やるべきこと”が見えてくる
模試を受ける一番大事なことは、受けた後の復習です。
「どの分野で間違えたのか」
「ケアレスミス?それとも知識不足?」
これをしっかり見直すことで、次にやるべきことが明確になります。
逆に言えば、復習しないと模試の意味は半減です。
うちでは模試の後に「どこができなかった?」とだけ聞いて、息子たちに自分で答えさせていました。
5. 本人の“やる気スイッチ”になることも
模試の結果を見て、本人が「やばい…」と思うことでスイッチが入るケースもあります。
親が言っても響かないことが、模試の判定一つで火がつく。
逆に、「思ったより取れてた」と自信になることもあります。
うちでも、模試を受けるたびに少しずつ「受験生らしく」なっていく様子がありました。
模試の結果に一喜一憂しすぎないことも大切
模試の結果に親が振り回されすぎると、子どもにプレッシャーを与えてしまいます。
私はできるだけ、
- 点数より「どこが苦手か」
- 判定より「次にどう動くか」
に目を向けて声をかけるようにしていました。
まとめ:模試は“現在地”を知るための地図
模試は、あくまで現時点の学力のスナップ写真です。
未来を決めるものではありません。
でもこの「地図」を持たずに受験を進めるのは、とても不安です。
だからこそ模試を上手に活用して、子どもと一緒に進路を考える材料として使ってほしいと思います。
受験生の親としても、模試の意味や活かし方を理解しておくことは、子どもを安心して見守るための武器になりますよ。
↓ランキングに参加しています。よろしければクリックいただけると励みになります😊
にほんブログ村
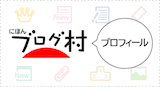

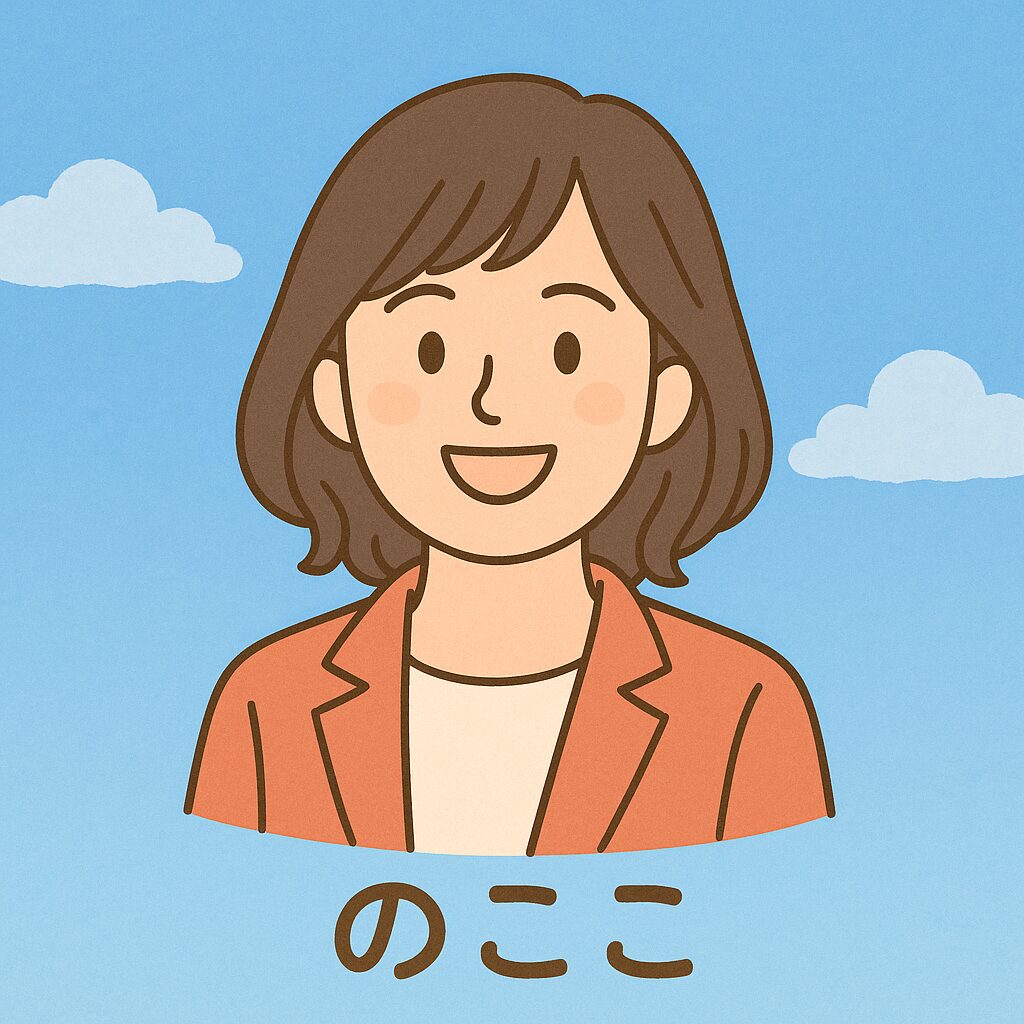

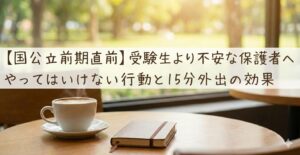


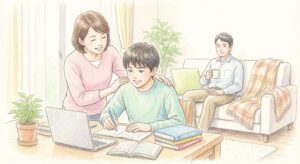
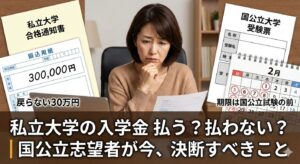


コメント