子どもが成長する中で、親として「こうなってほしい」と願うのは自然なこと。でも、その“期待”がいつの間にか子どもにプレッシャーを与えていないでしょうか。この記事では、双子の大学受験・子育てを経験した母の実体験をもとに、親の期待との向き合い方をお伝えします。
親の期待が子どもに与える影響
子どもが小さいころ、「期待すること」は自然なことだと思っていました。
「この子にはきっとできる」「頑張れば夢が叶う」と信じる気持ち。親として当たり前のように抱いてきた思いです。
けれど、大学受験を迎えたとき、私はふと考えるようになりました。
“私の期待って、もしかしてプレッシャーになっていない?”と。
模試の結果が思うようにいかなかったとき、「次は頑張ろう」と声をかけたつもりが、息子は少し苦しそうな顔をしていました。その表情を見た瞬間、私はハッとしました。
私の「応援の言葉」が、“結果を出さなきゃいけない”という重荷に変わっていたのかもしれません。
子どもは親の表情を敏感に感じ取ります。「信じてるよ」と言葉では言っても、心の中に“焦り”や“心配”があれば、すぐに伝わる。
それを双子の受験を通して痛感しました。
「親の夢」と「子どもの夢」は違う
私自身、「安定した職業についてくれたら安心」と思う気持ちがどこかにありました。
でも、子どもたちは「やりたいこと」「興味のある世界」を見つけたがっていました。
ある日、太郎が「都会の大学で学びたい」と話したとき、私は思わず「お金がかかる」と言ってしまいました。
経済的な不安、将来への心配……母親として当然の反応だったのですが、その言葉は太郎の夢を小さくしてしまったように感じました。
太郎は、地方の大学よりも、都会の大学の方が新しいことを学べるし、都会の有名企業に就職した。という気持ちがあったのでしょう。
一方、次郎は「地元で公務員になりたい」と言いました。同じように育てた双子なのに、性格も夢も全く違う。
その時、「親の価値観を押しつけないで、それぞれの人生を歩ませることが大切なんだ」と心から思いました。
“何になってほしいか”ではなく、“どんな人になってほしいか”を考える。
そう視点を変えることで、少しずつ気持ちが楽になりました。
「期待を手放す」=「信じて見守る」
親として「心配しない」ということはとても、難しいことだと思います。
ですが、心配しすぎると、その不安が子どもにも伝わってしまいます。
私が変わるきっかけになったのは、受験直前のある夜の出来事でした。
太郎が「もう無理かもしれない」と言ったんです。
私は思わず「そんなこと言わないで、最後まで頑張ろう」と返してしまいました。
でもそのあと、「今の子どもに必要なのは“励まし”ではなく“寄り添い”かもしれない」と気づきました。
それからは、「頑張ろう」ではなく、「ここまでよく頑張ってるね」と伝えるようにしました。
言葉を変えるだけで、子どもの表情がふっと柔らかくなったのを覚えています。
“期待を手放す”とは、“諦める”ことではなく、“信頼する”こと。
見守る勇気が、親にも必要なのだと感じました。
夢を応援するための5つのステップ
- まず「聞く」
「どうしてそう思ったの?」と、子どもの気持ちを聞くことから始める。親が話すより、まずは“耳を貸す”ことが大切でした。 - 否定ではなく「質問」で返す
「それでどうするの?」と問いかけると、子ども自身が考え始める。正解を与えないように気をつけました。 - 小さな挑戦を一緒に喜ぶ
模試の点数アップや努力の過程を「見てたよ」と伝える。結果よりも「プロセス」を認めることが、自己肯定感につながります。 - 比べない
双子だからこそ、つい比べてしまうこともありました。でも、それぞれの成長スピードや得意分野は違う。比較ではなく、「あなたはあなた」で接するよう心がけました。 - 信じる言葉で締めくくる
「大丈夫、あなたならできる」——この言葉は、親が差し出せる最大のエールです。
親も“期待を手放す練習”を
実は、子どもに「自由に生きてほしい」と言いながら、心のどこかで“自分の理想”を重ねていたのは私でした。
でも、太郎と次郎が大学生、社会人になり、それぞれ違う道を歩み始めた今、ようやく気づきました。
親の「期待」は、子どもを守るためのものでありながら、ときに“重し”にもなるということ。
だから今は、「頑張ってほしい」よりも「幸せでいてほしい」と思います。
子どもが心や体を壊してまで頑張らなければならない環境にいるときは、逃げてもいい。
逃げることは負けではなく、自分を大切にする勇気だと伝えたいです。
親も、子どもも、完璧でなくていい。
それぞれが自分のペースで生きていけるように。
“期待を信頼に変える”ことで、親子関係はもっと穏やかに、優しくなれると感じています
まとめ
「親の期待」は、時に子どもを苦しめることもあります。
でも、それを「信頼」に変えられたとき、子どもは安心して自分の夢を描けるようになるのだと思います。
双子の母として、こそだてはひと段落したのですが、まだまだ試行錯誤しています。
けれど、社会人として歩き始めたこれからも「陰で見守る勇気」を忘れずに、子どもたちの人生を静かに応援していきたいと思います。
にほんブログ村
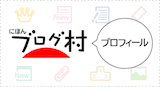

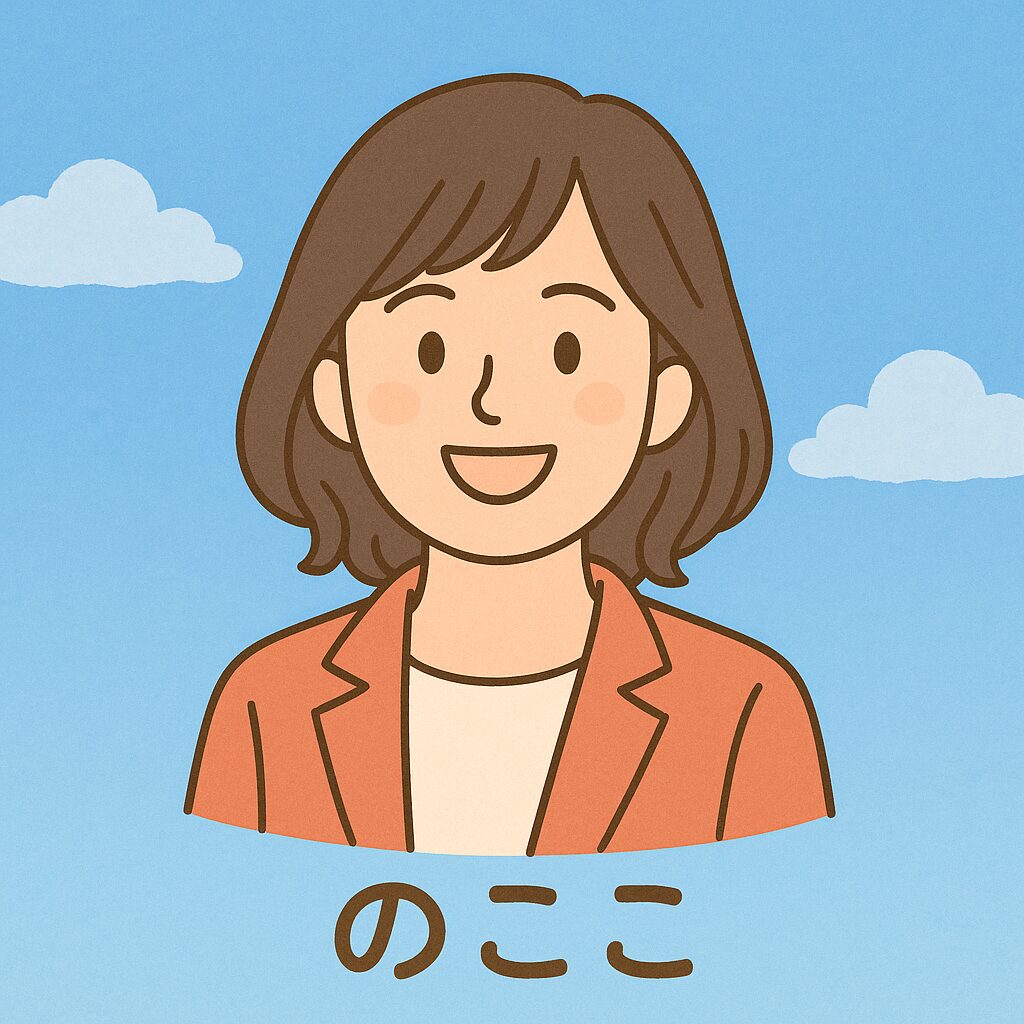








コメント