大学受験は「情報戦」と言われるほど、どれだけ正確で自分に合った情報をつかんでいるかが合否を分けるポイントになります。塾に通っていても通っていなくても、最終的に必要なのは「正しい情報をもとに自分で判断できること」。では、最低限どんな情報を調べておくべきなのでしょうか?
目次
1. 志望校の入試方式とスケジュール
- 一般選抜・総合型選抜・学校推薦型選抜など、どの方式で受験するのかを明確に。
- 出願期間、試験日、合格発表日などのスケジュールを必ずチェック。
- 特に 共通テスト利用入試 は大学ごとに科目や配点が異なるので要注意です。
2. 配点と科目の優先度
- 同じ大学でも学部によって配点はバラバラ。
- 国公立ならば、共通テストに配点が重いのか、二次試験が勝負なのか。
- 例えば「英語重視」なのか「数学と理科がカギ」なのかを知るだけで、勉強の効率が大きく変わります。
- 「苦手科目をどこまで伸ばすべきか」「得意科目で稼げるか」を見極める材料になります。
3. 過去問の傾向
- 出題形式(記述中心・マーク中心・英作文の有無など)。
- 難易度(共通テストとのギャップが大きい大学も多い)。
- 時間配分。
→ 過去問を数年分チェックすることで、勉強の方向性が見えてきます。
4. 合格最低点・倍率の目安
「どのくらいの得点を取れば合格できるのか」目標ラインを知ることで出願するかどうかの判断材料にもなります。合格最低点はその年によって変わるので、数年分をチェックすることをお勧めします。
倍率も前年度だけで判断せずに、数年分確認が必要です。案外、倍率は隔年ごとに高い低いを繰り返していることも多いです。ただし、数字に振り回されすぎないことも大事です。
5. 出願戦略(併願校・滑り止め)
第一志望だけでなく、確実に合格できる安全校 と 挑戦校 のバランスを考える。
滑り止めであっても、志望校と出願傾向が似ている大学を受験すると対策の負担が減る。受験料や試験日程の重なりも事前にシミュレーションしておく。
6. 学校生活や進学後の環境
サークル、就職実績、留学制度など。受験勉強のモチベーションアップにつながります。「大学に入ってからの自分」をイメージできるかどうかも鍵🔑。
親ができるサポートのポイント
情報戦といっても、受験生本人だけで調べきるのは難しいもの。親のサポートが大きな安心材料になります。
- 大学公式サイトを一緒に確認する
受験要項や日程は毎年変わることがあります。見落としがないようにチェック。 - 出願スケジュールをカレンダー化
試験日や締切をカレンダーに書き出すことは必須。抜け漏れなく視覚で確認が可能になります。 - 併願校のシミュレーションを手伝う
試験日程や受験料の重なりは大人の目線でサポートするとスムーズ。 - 情報の信頼性を確認する
ネット上の体験談は参考になる一方、古い情報も多いので「公式で裏取り」する姿勢を一緒に。
まとめ
受験はただ勉強を頑張るだけではなく、正しい情報を整理し、自分に合った戦略を立てること が成功のカギ。
「知らなかった」「もっと早く調べておけばよかった」という後悔を防ぐために、親子で最低限の情報を共有しておくと安心です。
にほんブログ村
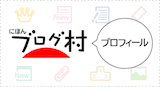

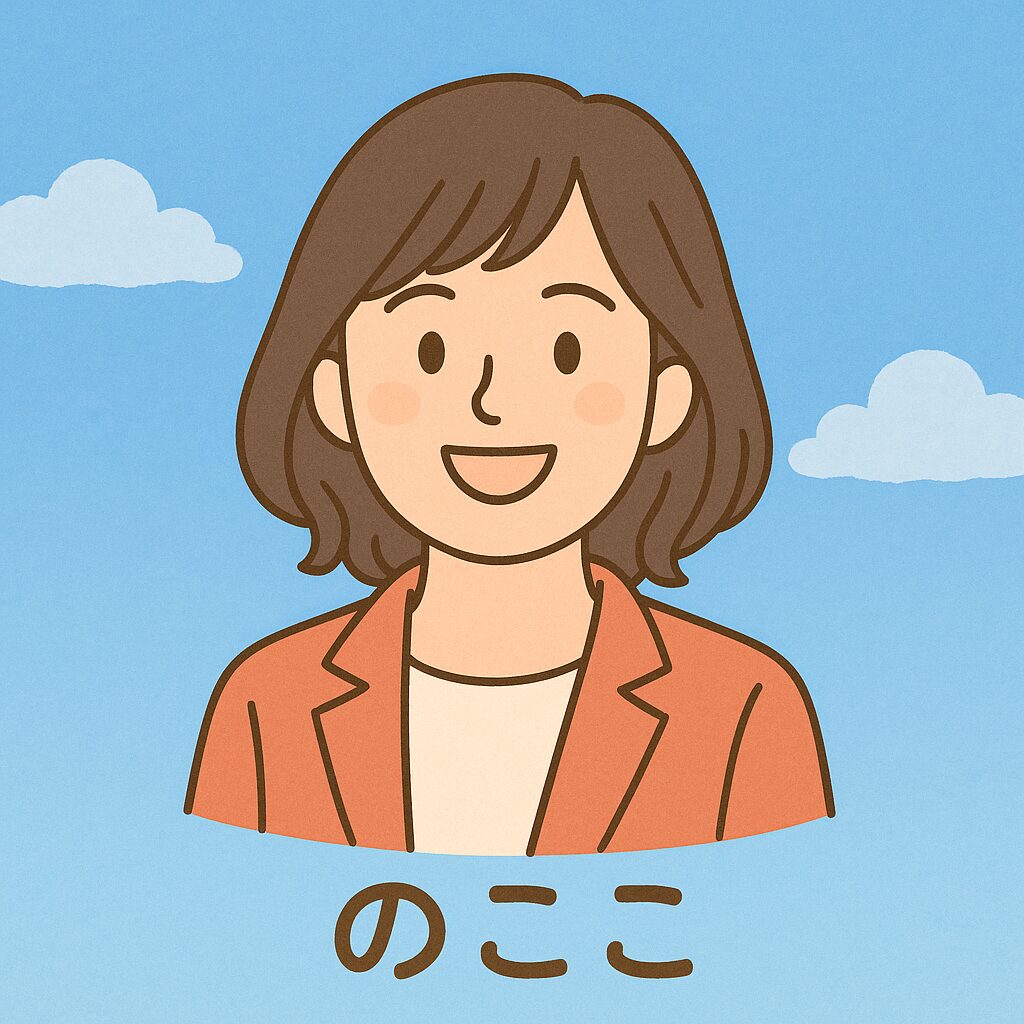



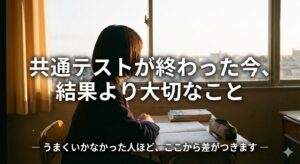
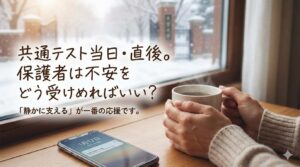
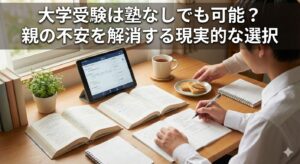

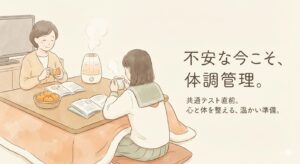
コメント